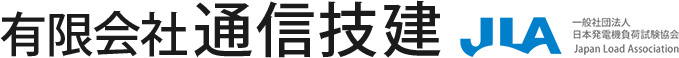|
法令
|
消防法
|
電気事業法
|
|
行政
|
総務省
|
経済産業省
|
|
点検対象物
|
消防設備機器
|
電気工作物
|
|
負荷点検方法と内容
|
第214号第24-3に基づく、定格出力の30%以上の負荷で、
30分運転後の電圧・電流値を測定し、消防点検報告書にそのデータを添付 |
負荷率や運転時間の規定が無いため、2~3分程度の無負荷運転を行い、
個々の電気工作物の電圧・電流値を確認 |
|
点検期間
|
消防機器点検 6か月
総合機能点検 1年 |
電気点検
月次または3か月 |
|
点検報告書の制作と書類提出者
|
ビル管理及び消防点検業者
|
電気点検業者
|
点検の重要性
点検の重要性について
月次点検等で行っている無負荷運転(空ふかし)だけでは万が一火災が発生しても正常に作動しない可能性があります。
そもそもなぜ点検が必要なのか?を一緒に考えてみたいと思います。
なぜ点検が必要なのか?
非常用発電機は始動しただけでは発電しない
月次点検等で行っている無負荷・軽負荷(30%以下)の運転では万が一火災が発生しても正常に作動しない可能性があります。一般的に各保安協会などで実施されている無負荷運転での性能点検とは異なる点検となりますので注意が必要です。(無負荷運転では運転性能の確認には不十分な為です)消防法で定められている負荷運転は、電気事業法の月次点検とは異なり、
消火活動に必要な非常時に動作させる各設備(スプリンクラーや消火栓ポンプ)を動かす為に必要な出力が実際に可能なのかを確認する大切な点検となります。

※スマホ表示は右にスクロールすると表がご覧いただけます。
カーボンが蓄積されると不具合の原因に
無負荷(エンジン始動のみ)・軽負荷(30%以下)の運転では湿ったカーボンが溜まり損傷や破損、火災などの原因になりかねません。定期的に負荷をかけて作動させることでカーボンを除去でき、自家発電機本来の役割を発揮することができます。